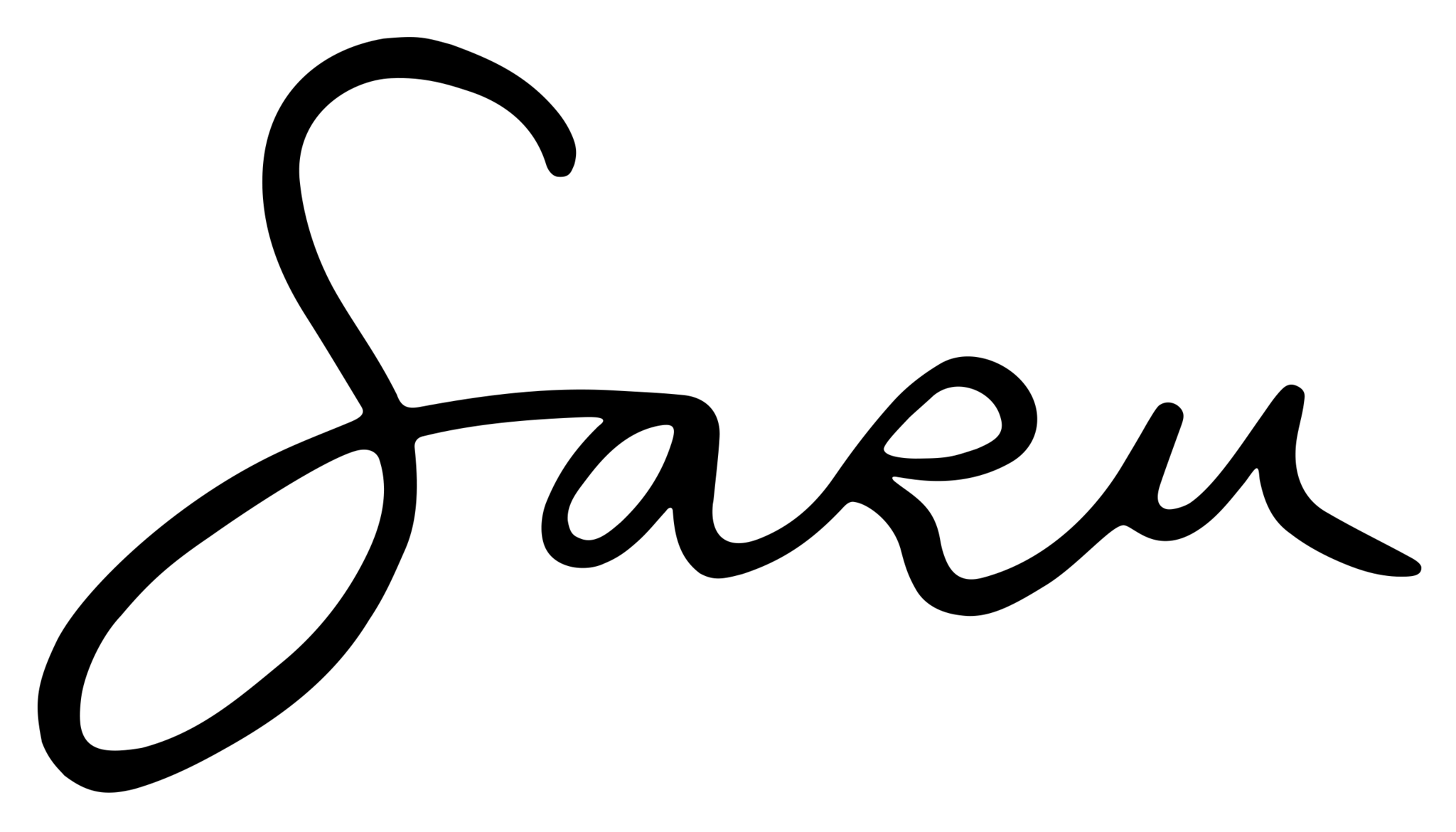2020/08/27 06:07
はい。
ここでは、私の練習以外のワークで、上達するのに役にたった経験を書いてみたいと思います。
私の先生であったハルトムート・ヘル先生は、ピアニストにも非常に体の使い方、支えを要求されます。難しいのは、先生が言う、「背中を沈めろ」という弾き方。音が、パン!という表面的で、平べったくて痛っとなる響きを防ぐため、弾く方が準備をして、深い音をだすためです。それはわかるのですが、外からみただけで、つかみにくかったのです。沈めると腕まで下がって弾きにくくなり、どうしたらいいかわかりませんでした。
ある声楽の講習会を聴講するためにワルシャワまで行った時に、声楽のレッスン以外の体のワークを指導する先生がいました。その先生に座り方をみてもらいました。脚の根元の骨が椅子にしっかりコンタクトがとれて、坐高が曲がらないよう、椅子の位置と高さをみつけていきました。かなり思い切った位置でしたが、長い坐高でぐにゃぐにゃとなりやすい背中が正しい位置になると安定して出せる音が出せるようになりました。
学生を卒業してからピラティスを始めました。そこで、呼吸を使って筋肉や骨の動きをエクササイズをやるのは、気持ちいいものだけでなく、私には、革命的なくらい体で緊張と緩和を体験しました。それ以来、音楽の作り方やフレージングをする際に必要な緊張と緩和が体で感じられるようになました。(頭でやっていると、どうしても浅くなる)
これは、私の腕をあげるのにとても役に立ちました。
ピラティスは5年ほどやって、ヨガで、独自のエクササイズで特許をとった先生のところで、今はやっています。
彼女の考え方は、正しい骨の位置に体をもっていくと呼吸が自由になり、動きも自由になるという考え方で、1時間半、正確に細やかな動きをやります。難しいのは、運動神経みたいなのをつかうのでなく、奥の筋肉や骨の動きの微妙な動きで変化するのを観察することです。
私は、体を動かすのが好きなので、ついつい速くなりがちで、注意されます。
動きと動きの間とか、吸うのと吐く呼吸の間に時間をかけたり、ゆっくり吐ききったりかなり丁寧に教えられます。
音楽にもこの丁寧さは、とても重要で、変わり目の弾き方がうまいと自然で綺麗に聞こえます。実は、この自然な音は、自然に弾くから、勝手にやってきてくれるのではなく、体の支え、抵抗を上手につかうからこそ、重力でものが沈むような音でなく、音がうかびあがってくるのです。
学生時代、ずっと先生が言っていたものは、こういうことでした。
卒業してから、体のワークをすることにより、体の仕組みを知って、論理的につかうことを知っていくと、先生の要求していることを置き換えていけます。
先生、こう言うことを要求していたのか。今更ながらに思います。
なので演奏が上手になったりするには、心の豊かな経験も大切な他、体への知識、経験が必要だと思います。
それらを知ることやワークすることは、とても興味深いし、私には、人生を豊にしてくれたし、痛い肩も治るし、とても感謝しています。
音楽を目指す方にもヨガ、ピラティスおすすめです。

森の中でエクササイズ。2020年3月